|
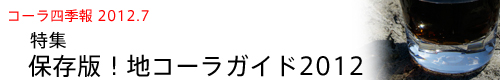
ここ数年、国内でご当地もののコーラがひそかなブームだ。一時期の「地サイダー」ほどの爆発的な広がりではないが、その土地の特色や素材をうまく取り入れた地域色豊かなコーラが誕生している。今回はそんな地コーラを取り上げてみたい。
地コーラが生まれなかった理由
地元の名産品の人気が高い日本で「地元のコーラ」は長く生まれなかった。その理由は日本におけるコーラの歴史に深い関係がある。
コーラが生まれた国・アメリカでは、ローカルの飲料メーカーがコーラ飲料を作ることは珍しいことではない。大量生産で均一的な製品を作るコカ・コーラやペプシなどと差別化を図るため、彼らは珍しい材料やフレーバーなどを採用した。その中で自然に生まれたのが、その土地の特産品を使った「地コーラ」であったと考えられる。
例えばシアトルのあるワシントン州では、特産の蜂蜜を使ったDRAFT HONEY COLA作られた。またロッキー山脈の麓の町では地元のハーブと湧き水を使ったWRANGLER Colaコーラがある。またShasta Cola やCragmont Colaなど山の名前のついたコーラは、元々はその周辺のきれいな水を使ってコーラを作っていた頃の名残であることが多い。
一方日本では明治時代以降、ラムネやサイダーが炭酸飲料の主役だった。当時はボトルを再利用していたため、メーカーはボトルが回収できる範囲でしか商売ができない。このため日本全国に小さなローカル飲料メーカーが数多く存在し、それぞれが独自のサイダーを作っていた。
しかし大量生産で低価格な製品を作る大手飲料メーカーの台頭により、ラムネ屋型のビジネスモデルは徐々に苦戦を強いられることになる。特に1956年のコカ・コーラの参入は多くのローカル飲料メーカーが廃業に追い込んだ。このような時代背景の中、ローカルの炭酸飲料も徐々に姿を消していった。
またコカ・コーラの参入でコーラという飲みものを知った日本の消費者に、「コーラ=コカ・コーラ」という固定観念が生まれた。この点が、コーラがサイダーと同じような飲料カテゴリと認識されているアメリカと大きく異なる。ある老舗のローカル飲料メーカーの当時の社長は「コーラはラムネ屋の敵だ」とコーラ飲料を絶対に作らなかったという。
このような理由で、日本では地コーラは長く作られることがなかった。
地サイダーの復活
だが2000年に入った頃からローカル飲料の状況が変わり始める。有馬サイダーやスワンサイダー・雲仙レモネードなどの地サイダーの復活が相次いだのだ。
その要因はいくつかあるが、一つはネット通販の発達によりニッチ商品を全国に販売できるようになった点。また地元での長い歴史のある復刻サイダーを地域振興に活用したいという重いとも結びついた。また飲料メーカーがボトルのワンウェイ化を進めた点も見逃せない。
当初は単に過去のサイダーを復刻させただけのものが多かった。しかしこのブームが大きくなるにつれ、各地で地元の原材料を取り入れ地域性をアピールした「ご当地サイダー」が作られるようになった。小豆島のオリーブサイダーや宮崎県の地サイダー(日向夏味)などがその代表だ。
しかし、地サイダーがご当地モノの地位を固めた後も地コーラはなかなか現れなかった。
伝説の地コーラ
そんな中、地元の原材料を使ったコーラづくりを決心したのが沖縄県伊江島の物産センターだった。島の湧き水と黒糖を使ったコーラを企画し、佐賀県の友桝飲料へ開発を委託。そうして生まれたのが「イエソーダ・ブラックケインコーラ」であった。
このコーラの成功を受け、ようやく各地で地コーラが作られるようになった。静岡県産のお茶を使った「しずおかコーラ」や、宗谷岬の塩を使った「宗谷の塩コーラ」など個性豊かなコーラが登場したのはこの数年のことだ。
以前このブラックケインコーラを企画された方にお話を伺ったところ、地コーラを作る決断の裏にはある伝説のコーラの存在があったという。
沖縄のコザ(現沖縄市)で作られたコーラ、KOZA COLAである。ロックの町として知られるコザでコーラが作ったのは、語呂だけでなく米軍基地を抱えるこの地域ならではの事情があったともいわれる。反骨精神が生んだ、ロック魂溢れるコーラであったようだ。
残念ながら6000本ほど作られたのみで生産終了となったそうだが、このコーラの存在が日本の地コーラの背中を押したと言っても過言ではないだろう。
2012年7月現在、日本では8種類の地コーラが確認されている。数こそ地サイダーに遠く及ばないが、それぞれ地元の特色を生かしたオリジナリティの高いものばかりだ。
宗谷の塩コーラ |
 |
販売県 |
北海道 |
販売者 |
ノース・クレール |
価格 |
180円 |
主な販売場所 |
土産物店など |
通販 |
可 |
涼しげなブルーの液色と熊のイラストの対比が印象的な、北海道産の地コーラ。販売者のノース・クレールは、ラベンダー線香などを手掛ける北海道土産専業メーカーだ。
塩スィーツブームの後期に発売されたこのコーラの特徴は、宗谷産の塩を使用している点。塩+コーラを組み合わせた(多分)世界初のコーラで、2012年にサントリーが「ペプシソルティウォーターメロン」で追従したほど。そのチャレンジ精神は素晴らしい。
北海道のお土産物屋のほか、通販でも購入可能。最近はビックカメラ(なんば店)のお酒コーナーにも出没するようになった。 |
しずおかコーラ |
 |
販売県 |
静岡県 |
販売者 |
木村飲料株式会社 |
価格 |
200円 |
主な販売場所 |
県内土産物店(SA・新富士駅など)・木村酒店 |
通販 |
可 |
静岡県の飲料メーカー、木村飲料の緑茶コーラ飲料。コーラとしては珍しく、2011・12年のモンドセレクション金賞を受賞している。
原材料には静岡県産の緑茶を使用。後味にほのかに香る緑茶の風味が新しい。お茶を使ったサイダーはいくつかあるが、コーラにしたのは本品が初めてだ。カフェインは入っていないので、どのあたりがコーラなのかは微妙なところだ。
2011年より富士山のデザインを取り入れたオリジナルのエンボスボトルを採用。最近はボトルに着せられる清水エスパルスのユニフォームセットをリリースするなど、郷土愛溢れる地コーラである。 |
 |
 |
木村酒店では同社の炭酸飲料やシロップが1本単位で買えるのが嬉しい。 |
オリーブ・コーラ |
 |
販売県 |
香川県 小豆島 |
販売者 |
有限会社 安田商事 |
価格 |
200円 |
主な販売場所 |
小豆島オリーブ園 |
通販 |
可 |
オリーブの産地で有名な、香川県小豆島の地コーラ。オリーブを連想させる深緑のボトルが印象深い。
原材料にオリーブ果汁エキスが使用されている。フレーバリングの目的としているようで、コーラ自体は「無果汁」扱いだ。
小豆島は他にも「オリーブサイダー」や「醤油サイダー」など多くの地サイダーを輩出している。侮りがたし小豆島。 |
広島コーラ |
 |
販売県 |
広島県 |
販売者 |
齋藤飲料工業株式会社 |
価格 |
200円 |
主な販売場所 |
県内SA、道の駅みはら、齋藤飲料前自販機 |
通販 |
可 |
広島県福山市の飲料メーカー・齋藤飲料工業が手掛ける地コーラ。鯉と紅葉と名古屋城を取り入れたパッケージデザインが秀逸だ。
本品は広島県産はっさく果汁を1%している。はっさくの苦味とコーラとの相性が良く、レベルの高いコーラである。
齋藤飲料工業は福山コーラや宮島コーラも製造しているが、自社で販売しているのは本品のみ。本社の前にある自社製品がずらりと並んだ自販機は一見の価値あり。 |
 |
道の駅みはら 神明の里売店にて |
福山コーラ |
 |
販売県 |
広島県 福山市 |
販売者 |
トゥエニーワン |
価格 |
198円 |
主な販売場所 |
トゥエニーワン、イトーヨーカドー福山店・岡山店、福山SA下り線、福山市の居酒屋 |
通販 |
不可 |
福山市の酒屋「トゥエニーワン」が販売するコーラ飲料。黒地に福山のシンボルであるバラをあしらったラベルには、ちょっと大人の雰囲気が漂う。
強炭酸で人気の高い「福山ハイボール」を踏襲し、このコーラも炭酸を強めに仕上げてあるのが特徴。甘さも控えめで、そのままはもちろん割り材としても秀逸な出来だ。
通販の取り扱いは今のところなく、取扱いは福山市内および岡山のイトーヨーカドーのみ。現地に行かないと買えない、入手難易度の高い地コーラである。 |
 |
イトーヨーカドー 福山店にて |
宮島コーラ |
 |
販売県 |
広島県 宮島 |
販売者 |
みやじま華屋敷 |
価格 |
250円 |
主な販売場所 |
土産物店・木村飲料 |
通販 |
可 |
世界遺産・厳島神社のある宮島の観光物産店「みやじま華屋敷」のオリジナルコーラ。製造は広島県の斎藤飲料工業である。
桜島にちなんだ、うすい桜色の液色が特徴。ラベルには紅葉とともにみやじま華屋敷のエンブレムが燦然と輝く。
店の前のカウンターで焼き牡蠣と並んで販売されていたので一緒に食べてみた。牡蠣は美味だったが、コーラとのシナジー的なものは特になかった。 |
 |
みやじま華屋敷のカウンターにて |
古賀飲料コーラ(コガ・コーラ) |
 |
販売県 |
福岡県 |
販売者 |
みやま市商工会 |
価格 |
200円 |
主な販売場所 |
船小屋温泉郷 |
通販 |
不可 |
探偵!ナイトスクープで一躍有名になった福岡・古河飲料のコガ・コーラ。それを復刻されたのがこの本品である。その話題性のあるネーミングは、KBC九州朝日放送「ドォーモ」の爆笑ネーミング大賞を受賞している。
原材料には船小屋の天然炭酸鉱泉を使用している。土産物屋や通販では一切販売せず、取り扱いは船小屋温泉郷のみというストイックさ。
発売当時は販売所の開いている時しか購入できず、また行ってみないと入荷されているか分からないという超ハードモードだった。現在は自販機が設置され、とりあえず現地まで行けば購入できるようになった。
詳細→ 四季報津々浦々 伝説のコガコーラを求めて |
 |
 |
ギリギリ感の漂う自販機(左)と、ネーミング大賞受賞記念看板(右) |
イエソーダ・ブラックケインコーラ |
 |
販売県 |
沖縄県 伊江島 |
販売者 |
伊江島物産センター |
価格 |
200円 |
主な販売場所 |
伊江島の土産店、わしたショップ、千成屋など |
通販 |
可 |
日本の初の本格的地コーラ。沖縄本島の北西に浮かぶ伊江島の地コーラで、原材料に島の湧き水「湧水(わじい)」と島産の黒糖を使用している。
伊江島だけでなくわしたショップなどの沖縄物産ショップで取り扱いがある。また大阪・なんばの千成屋では喫茶コーナーでこのコーラを飲むことができる。
入手は比較的容易だが、伊江島の恵みがぎゅっと詰まったこのコーラはぜ現地で飲むことをオススメしたい。
詳細→ 四季報 津々浦々 美しい島の地コーラを訪ねて |
 |
伊江島フェリーターミナルのお土産物屋 |
進化する地コーラ
さらに地コーラは清涼飲料の域にとどまらず、新たなスピンオフ商品を生み出している。
木村飲料はしずおかコーラのブランド化に向け、様々な関連商品を開発。業務店用に5倍濃縮シロップを販売し、チューハイなどの割り材としての使い方を提案している。また静岡ご当地食品として静岡コーラドロップスなどのお菓子への展開も始めている。
また日本の地コーラの先駆け、伊江島ブラックケインソーダはカバヤの「地ラムネ&地サイダーキャンディ」のフレーバーとして商品化されている。
さらに伊江島では伊江島さんサトウキビで作ったラム酒「イエラムサンタマリア」を使った、日本初のアルコール系地コーラを発売。OKINAWAN LIBRE(沖縄の自由)と名付けられたラムコーラは、地コーラの新たな可能性を切り開いた。
これから益々広がっていきそうな日本の地コーラ。コーラ白書は応援します。
|