| コーラ四季報 2004年4月号 |
|---|
| 特集 |
| コーラを撮る |
| 対決! |
| 今月の一冊 |
| 今月の珍品 |
| お便りコーナー |
| バックナンバー |
| 連載記事 |
| 小説募集中 |
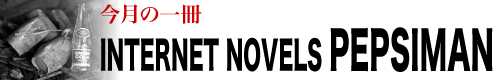
中橋 一朗
 「これ、今月の課題図書ね」
「これ、今月の課題図書ね」
そう言われて中本から受け取ったのが、本書である。聞けば、昔PEPSIがインターネットで公募したリレー小説を書籍としてまとめたものであるという。その時は首を捻るばかりだったが、今考えると、そんなこともあったかもしれないという気になってくる。
恐らく広告代理店の人間が書いたと思われる「まえがき」によると、インターネットが大流行、ニューメディアとして史上空前の大ブームなのだそうだ。そして本書は、「インターネットを利用した、新しい型のワード・クリエイティブゲーム『P.E.P.』を一冊にまとめたもの」とある。
つまり、まず監修の鴻上尚史がペプシマンをネタに3つのストーリー(の、プロローグ部分)を書き、PEPSIのウェブサイト上に公開する。読者が気に入ったストーリーの続きを書き、電子メールで投稿。その中から鴻上尚史が選んだ優秀作品が再びウェブサイトに公開され、読者はまたその続きを投稿する・・・。とまあ、メディアがニューな割には手法が古典的なのだが、取っつきやすいことは確かだ。
奥付を見ると1996年発行とある。インターネットの存在自体が珍しくて、とにかくインターネットって凄いんだ、何でもできるんだ、という気分があった頃だと思う(今でもそうかもしれないけど)。そういえばコーラ白書がスタートしたのも1996年末のことだった。ペプシマンの等身大看板を背負って電車に乗ったりしたことも、今では想い出の1ページだ。当時お世話になった酒屋のいっちゃん氏、お元気ですか? すっかりご無沙汰してしまい、申し訳ありません。
それはともかく、鴻上尚史も相当浮かれていて、要するにこれは読者も物語作りに参加できる小説なのだ、あなたのイマジネーションが試されているのだ、という趣旨のことを述べている。インターネットでは誰もが作家になれる、そんな可能性に気付いていたのは流石と言えるが、優秀な作家になれるかどうかはやはり本人次第だ。私はむしろ忍耐力を試されていると感じた。
本文は3つのプロローグから始まり、途中で分岐しながら全部で24の結末(打ち切りを含む)を迎える。昔流行ったゲームブックのようなイメージだ。枝分かれを後戻りしやすいように、本書には栞の紐が2本付いている。全体には辛い評価となったが、このささやかな配慮がとても嬉しかったことを記しておく。
ちなみに総務省の資料によれば、携帯電話等も含めたインターネットの人口普及率は1997年末時点で9.2%。2003年末時点では60.6%に達している(残念ながら96年時点でのデータは見当たらなかった)。
DATA
P.E.P 著/鴻上尚史 監修/ぶんか社/1996年
ISBN4-8211-0523-3
[コーラ白書] [HELP] - [English Top]
Copyright (C) 1997-2014 Shinsuke Nakamoto, Ichiro Nakahashi.
当ウェブサイトに記載されている会社名・商品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です