| 四季報 |
|---|
| 特集 |
| コミケ |
| 津々浦々 |
| Collectibles |
| 珍品 |
| 小説 |
| お便り |
| バックナンバー |
| 連載記事 |
| 小説募集中 |

水や茶とジュースとを決定的に分けるもの、それは甘味料の存在である。今日の清涼飲料の発展は甘味料無しではあり得なかったといっても過言ではあるまい。ほとんどの炭酸飲料で糖は炭酸水の次に多く含まれているし、欧州では新人工甘味料・アセサルフェ−ムKがダイエット飲料市場を席巻している。しかし甘味料に関しての情報はそれほど一般的ではなく、多くの人が深く考えることなく口にし、その味を楽しんでいる。意外と知られていない甘味料について少し勉強してみようというこの企画、第1回は、砂糖やコーンシロップ等最も身近な甘味料「糖質」についてである。
1-1. 糖とは何ぞや?
私は定義というやつが大嫌いである。このあたり自分が化学者に向いていないことを実感するのだが、真似事でも糖を論じるとあってはその定義を明確にしないわけにはいかない。嫌だけど、やる(内容的にちょっと難しくなると思うので、化学の嫌いな人は次章へ速やかに進むこと)。
糖といえば甘くて水に溶けるものといったイメージがあるが、それは糖全体の説明としては正しいとはいえない。糖は定義では炭水化物と同義で、かつては Cn(H2O)n で表せる化合物を指すものであった。しかし糖科学や糖鎖工学の発展によりこの定義では不十分となり、現在では 「ポリヒドロキシアルデヒドまたはポリヒドロキシケトンおよびその縮合体ならびに誘導体」 とされる化合物の総称となっている。ほら、分からなくなったでしょ?
その糖のうちこれ以上加水分解されない最小ユニットを「単糖」、単糖が2つくっついたのを「二糖」、数個くっついたのを「オリゴ糖」、たくさんくっついたのを「多糖」と呼ぶ。多糖の代表といえば紙や木の主成分・セルロースであり、こいつらはでかすぎて甘くないし水にも溶けない。ここまで来ると本特集の趣旨から外れてしまうので、ここでは甘味料として使用されているいくつかの糖に絞って説明を続けよう。
1-2. 一粒300m、グルコース
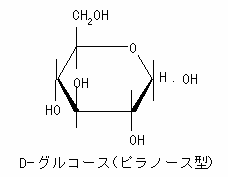 単糖類はアルデヒド基(-CHO)を持つアルドースとケトン(C=O)をもつケトースに分類される。そして自然界に最も多く存在するアルドースはグルコースと呼ばれる単糖である。別名ブトウ糖とも呼ばれるこの化合物はデンプンやグリコーゲンの構成要素として知られる、いわば生物のエネルギー源。我々は一粒のグリコに含まれるグルコースのおかげで300mも走らされてしまうのである。
単糖類はアルデヒド基(-CHO)を持つアルドースとケトン(C=O)をもつケトースに分類される。そして自然界に最も多く存在するアルドースはグルコースと呼ばれる単糖である。別名ブトウ糖とも呼ばれるこの化合物はデンプンやグリコーゲンの構成要素として知られる、いわば生物のエネルギー源。我々は一粒のグリコに含まれるグルコースのおかげで300mも走らされてしまうのである。
グルコースの研究の歴史は古く、1792年にLonitzによって蜂蜜から発見され、1802年にProutによって単離されて以来膨大な研究がなされている。水に良く溶け、しょ糖(砂糖)の約74%の甘みを持つ物質で、天然ではブドウの汁に存在している。砂糖より甘みが少ないため単体で甘味料として使用されることはないが、コーンシロップの成分として影でジュースを支える存在である。なおJIS規格の飲料ではJIS規格のブドウ糖を使用することが義務づけられている。
1-3. 最強最甘(?)の糖・フルクトース
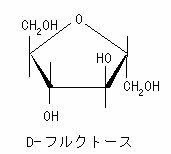 では天然に最も多く存在するケトースは? というと、それはフルクトースである。果糖とも呼ばれるこの糖は果実や蜂蜜の中に多量に存在することで知られ、1880年に Jungfleisch らによって初めて結晶として単離された。この糖の特徴は何といってもその甘さである。甘味度は砂糖の約1.7倍(173%)、これは天然の糖分としては群を抜いて高い。甘みが強いぶん使用量を減らすことができるため、日本では
Coca-Cola light
や
TaB Clear 変わってしまった。
などのローカロリーコーラに使用されている。
では天然に最も多く存在するケトースは? というと、それはフルクトースである。果糖とも呼ばれるこの糖は果実や蜂蜜の中に多量に存在することで知られ、1880年に Jungfleisch らによって初めて結晶として単離された。この糖の特徴は何といってもその甘さである。甘味度は砂糖の約1.7倍(173%)、これは天然の糖分としては群を抜いて高い。甘みが強いぶん使用量を減らすことができるため、日本では
Coca-Cola light
や
TaB Clear 変わってしまった。
などのローカロリーコーラに使用されている。
1-4. 廉価コーラの友、異性化液糖
スーパーの安いコーラの原材料の中に「コーンシロップ」という言葉を見つけ、不思議に思った経験はないだろうか。トウモロコシからシロップが取れるというのは何だか奇妙な話である。このコーンシロップという代物、実は上記のグルコースとフルクトースの混合物の事なのである。
作り方はこう。まずトウモロコシからデンプンを取り出す。何故トウモロコシかというと、値段が安いからである。それにアミラーゼ等の酵素を作用させるとデンプンは加水分解され、主としてグルコースからなる糖液が得られる。これにさらにグルコースイソメラーゼとよばれる酵素で処理すると、グルコースの一部がフルクトースに変化(異性化)する。この混合糖液が異性化液糖、通称コーンシロップと呼ばれるものなのである。ちなみにアイスコーヒーに付いてくるガムシロップの主成分もこのコーンシロップだ。
JISではさらに細かい分類がなされており、フルクトース含有率が50%未満のものを「ぶどう糖果糖液糖」、50%以上90%未満のものを「果糖ぶどう糖液糖」、90%以上のものを「高果糖液糖」と呼んで区別している。この異性化糖は砂糖より安く、甘いため現在殆どのコーラに使用されている。ただ砂糖にくらべて味の深みに欠け、単体では単調な印象を与えるのでCoca-Colaなどの正規コーラでは砂糖と併用する例が多い。異性化糖のみを使用したコーラには、 PEPSI Cola や Virgin Cola などがある。
1-5. キングオブシュガー・スクロース(砂糖)
さて真打・砂糖の登場だ。化学の世界で「スクロース」という名を頂戴したこの糖は、上記の単糖・グルコースとフルクトースが結合した構造を持つ二糖の一種である。ほとんどすべての植物に広く存在する糖で、工業的に甘薯(サトウキビ)より精製する事から「ショ糖」と呼ばれる事もある。今日ほとんどの菓子、飲料に使用される糖類の王様である。
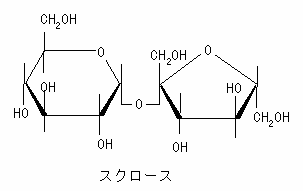
砂糖の最大の特徴は何といっても味が良いことである。甘さでは果糖に及ばないものの、その深みのある甘さ・旨さは他の糖の追従を許さない。現在様々な甘味料の研究がなされているが、その究極の目的は「砂糖と同じ味を再現する事」といっても過言ではないだろう。全ての甘味料の甘さの度合いを示す指標「甘味度」が砂糖の水溶液を基準としている事からもこの糖が甘味料研究の中心にいることが窺える。
また精製した糖液を攪拌しながら濃縮・結晶化すると粒子の細かい高純度の砂糖「グラニュー糖」が得られる。グラニュー糖は水に良く溶け、また不純物が少ない(純度99.8%以上)のでコーヒーや紅茶・清涼飲料などに使用される。喫茶店に置いてあるサラサラな砂糖の正体はこれなのである。砂糖のみにこだわったコーラとしてカフェインX2で有名な Jolt COLA の名が挙げられる。
1-6. 台所の魔術・マルトース
現在ではほとんど失われてしまった家庭の技術の中に、水飴作りというのがある。デンプンと水と麦の芽を鍋にいれうまい具合に加熱してやるととろみのある糖液が得られる。麦芽の酵素がデンプンと反応する事によってできたこの糖液の主成分はマルトース(麦芽糖)と呼ばれる二糖である。この糖はグルコース2分子がくっついた構造をしており、砂糖の約32%の甘さを持つ。あんまり甘くないので飲料の甘味料として使われることは少ないが、アスパルテーム等人工甘味料の担体として使用されている。
また同じグルコース2分子からなる二糖でトレハロースと呼ばれるものもある。これは昆虫の体液などに見られる糖で、マルトースとはグルコースのくっつく方向が異なる。マルトースより少し甘いため(砂糖の45%程度)甘味料としては使いやすいのか、グリコの牛丼や「朝CAN」などに使われている。今後の応用が期待される糖だ。
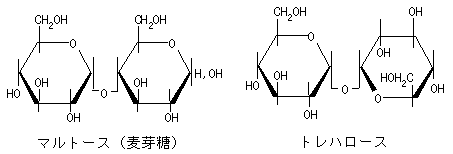
1-7. おナカのミカタ、オリゴ糖
最近機能性食品として注目されている糖といえば、ご存知オリゴ糖である。オリゴとは少数を意味するギリシャ語であり、オリゴ糖とは一般には単糖が3〜10個程度つながった糖を指すらしい。別に「お腹にいい」などという意味ではないので注意が必要だ。オリゴ糖は小腸で吸収されず大腸に達し、ビフィズス菌を活性化させてお腹の調子を整えたる働きがある。その上虫歯や便秘の予防、血糖値の調製までやってくれるのだから何と都合の良いことか。ありがとう、オリゴ糖。
代表的なオリゴ糖としてはグルコースを枝をつくって数個結合させたイソマルトオリゴ糖や大豆から得られる大豆オリゴ糖等があり、それぞれ砂糖の50〜70%くらいの甘さがある。オリゴ糖を含む飲料には超健康コーラ「健やかコーラ」やポッカの5回振る系飲料「ふんわりピーチ」などがあるが、両方とも他の甘味料と併用されている。
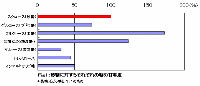
|
さて次回は甘味料概論 第2回、糖アルコール編である。今話題のキシリトールやお腹に来る(笑)エリスリトールなどを紹介する予定なので、乞うご期待! というか、ほんまに終わるんかこの企画!?
参考文献
- 「糖化学の基礎」
-
阿武喜美子・瀬野信子著 講談社サイエンティフィック
糖化学について詳しく述べた学術書。これ一冊あれば糖の化学的側面はほとんどカバーできる。 - 「有機化学・下」
-
R.T.MORRISON・R.N.BOYD 著 東京化学同人
豊富な図と回りくどい説明が魅力の化学の学術書。院試を共に戦った我が戦友でもある。 - 「生命にとって糖とは何か」
-
大西正健著 講談社ブルーバックス
ご存知ブルーバックスシリーズの1冊。糖の機能を分かりやすく説明した名書である。 - 「清涼飲料の常識」
-
(社)全国清涼飲料工業会・(財)日本炭酸飲料検査協会
清涼飲料に関わる人必携の一冊。飲料に関するエピソードからJIS規格までとにかく内容が豊富。
[四季報 1999年1月号] [コーラ白書] [HELP] - [English Top]
Copyright (C) 1997-2000 Shinsuke Nakamoto, Ichiro Nakahashi.