> 四季報
| 2001年4月号 |
|---|
| 特集 |
| 第2特集 |
| 津々浦々 |
| Collectibles |
| 珍品 |
| 今月の一冊 |
| お便り |
| バックナンバー |
| 連載記事 |
| 小説募集中 |

中本 晋輔
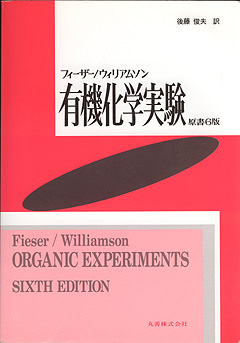 大学で化学を専攻する学生のほとんどは、3年目に「学生実験」の授業を受けなければならない。普通の講義の数倍の単位数をもつこの必修科目は研究室配属への最大の関門であり、これを何とかしかしないと卒業もできない。拘束時間も長いためこれまでのバイトやサークルに明け暮れたキャンパスライフは変更を余儀なくされ、自由な大学生は一転つねに課題に追われる身となる。
大学で化学を専攻する学生のほとんどは、3年目に「学生実験」の授業を受けなければならない。普通の講義の数倍の単位数をもつこの必修科目は研究室配属への最大の関門であり、これを何とかしかしないと卒業もできない。拘束時間も長いためこれまでのバイトやサークルに明け暮れたキャンパスライフは変更を余儀なくされ、自由な大学生は一転つねに課題に追われる身となる。
私は学生実験にあまりいい思い出はない。ただその中で手の上で濃硝酸のビンを割って手首まで黄色くなったこと(註1)と並んではっきり記憶に残っているのが、有機実験の指定参考書であった本書である。この本は濾紙の折り方や装置の組み方など実験の手順を事細かに説明したもので、これだけでも十分面白いのだが、私のなかで本書を決定的なものにしたのは「コーラシロップからのカフェインの抽出」という章の存在であった。
★ ★ ★
この本は化学の理論や式などを並べた参考書ではなく、「どのように実験をするか」に主眼を置いた実験書と呼ばれるものだ。器具の名称を説明する「実験準備」から始まり有機実験に欠かせない「クロマトグラフィー」「単離」「精製」といった手法はもちろん「ガラス細工」「化学文献の検索」などの2次的なものまでありとあらゆる実践のシーンを例を用いて説明した名著である。そしてその第7章、天然物から化合物を抽出の例としてコーラと紅茶が登場している。
この章の始めには「予習」としてカフェインについての詳しい説明がある。「摂取すると覚醒をもたらすので、覚醒剤の主成分である」(マジか?)という表記にはドキッとさせられる。また「カフェインは米国で最も乱用されている薬物である」というあたり、著者はカフェインに対してあまり好意的ではないようだ。有機化学者らしくカフェインを1つの「物質」として淡々と説明しているくだりはなかなか面白い。
また彼らはコーラについても言及しているが、その中に興味深い部分をみつけた。
「清涼飲料自動販売機では、コーラシロップを炭酸水で割っている」
現在アメリカでは缶の自販機が一般的で、カップベンダーを見かける機会はほとんどない。ではこの「清涼飲料自動販売機」とは何を指しているのだろうか。原本を読んでいないので何とも言えないが、これは「ソーダファウンテン」の事ではなかったのだろうか。現在アメリカでこの装置はほぼ絶滅しているが、本書の第一版は1937年(!)に発行されており、あるいは当時主流だったファウンテンに関する記述なのかもしれない。
本書の特徴である実験項はまさに手取り足取りといった感じで、実験の過程やテクニックを教育的立場から詳細に述べてある。化学に関するある程度の知識があれば、誰でもカフェイン抽出の方法を習得することができる。ただ抽出にジクロロエタンを使っているので、自宅でするには少々難がある。
実際にやってみよう!
ここまで書かれればあとは実際にやってみるしかない。実は、私が研究室に入って間もないころ、この実験を試みたことがあるだ(教官にどれだけ訴えても許可は下りないことは分かっていたので、学会のスキにこっそりと実行。もう3年前の話なので多分時効だ)。ところが、いきなり一行目でつまずいてしまった。
「市販のコーラシロップ50ml」
・・・コーラシロップってどこで売ってんねん? 注入中のカップベンダーに手を突っ込むことも考えたがタイミングが難しく、結局コーラは断念。りぷとんのティーバッグから抽出することにした。
ひたすら本の指示どおりにやって、得られたのは怪しい色の粉末。薄い緑色はカフェイン一水和物特有のものである。恐る恐るなめてみると、マイルドな苦味が口に広がる。決して不快ではなく、むしろ爽やかな苦味だ。「カフェインてこんな味なんや」と妙に感動したのを覚えている。
★ ★ ★
有機化学実験の定番ともいえる本書だけに、ほとんどの大きな書店で取り扱っている。最近第7版が出版されたが、コーラの実験はそのままであったのは嬉しいところだ。コーラと化学に興味がある方には必読の一冊といえよう。
(註1)キサントプロテイン反応。
[コーラ四季報2001年4月号] [コーラ白書] [HELP] - [English Top]
Copyright (C) 1997-2001 Shinsuke Nakamoto, Ichiro Nakahashi.